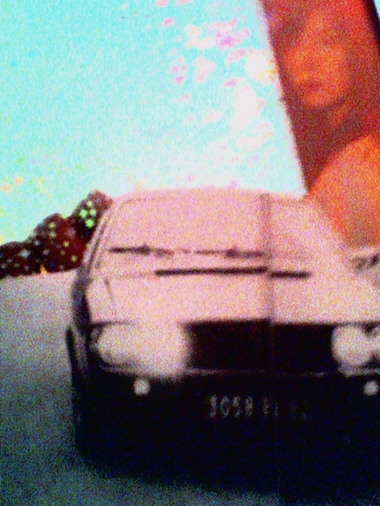
僕は大学生の頃、富士山の麓にあるゴルフ場のレストランでアルバイトをしていた。接客業の苦手な僕は、厨房での調理補助を選び、皿洗いから始まり、米を研いだり、野菜を切ったり、最後は調理場で揚げ物やチャーハンなどを作るまでになった。この頃から料理をすることが得意になり、あれから20年が経った今でも家の台所で家族のために料理をすることは多い。
そのレストランは全国に展開していたので、店長や社員のシェフは地元の出身という訳ではなく、何がしかの事情があってそのゴルフ場へ配属されていた。パンチパーマでいつも真っ赤な顔をしている料理長(いつも陰でパンチというあだ名をつけて呼んでいたため本当の名前は憶えていない)、九州出身でいつも気軽に話しかけてくる背の低いシェフ福島さん、地元のサーファーで僕といちばん仲良くしていたアルバイトの小宮さん、その三人の他には地元のパート主婦が数名働いていた。
小宮さんとは、アルバイトが終わると、よくアメリカ人の経営している富士吉田のバーへ通った。ニューヨーク出身のアメリカ人の夫がカウンターに立ち、日本人妻が奥のキッチンで料理をしているバーで、その周辺に在住している外国人の溜まり場となっている場所だった。僕と小宮さんは、そこでブラジル人の友達をつくって遊んだりしていた。僕は当時、シェイクスピアを専攻していて、アメリカ留学もしていたので英会話は得意な方だったし、小宮さんも昔、米軍基地のアメリカ人女性と交際していたことがあったりで、二人とも外国人と交流することを楽しむタイプだったからだ。
小宮さんと僕で協力しながら、引越しを手伝ったことが二回ある。一人は、そのバーで友達になった日系ブラジル人のエドだ。エドは日本に出稼ぎで来ていた。日系ブラジル人ばかりが集まるパーティーに連れていってもらったり、彼の運転するスポーツカーで早朝までドライブしたりして何回か一緒に遊んでいた。あるとき、彼が静岡の豆腐工場で働くことになり、小宮さんのマークⅡワゴンで引越しの手伝いをすることになった。
エドの新しい住所は古い一軒家で、荷物を運び入れたとき、すでに2人のブラジル人が住んでいた。一人は大柄で少し悪そうな白人男で、ずっと機嫌が悪そうに台所に腰掛けていた。もう一人は、40代くらいの親切そうな中年日系ブラジル人で、僕らに対して、「本当の友人っていうのは片手で数えるほどしかいないもの」と微笑みながら語りかけてきた。きっとエドの引越しを手伝ってあげたことを感謝していたのだろう。
もう一つの引越しは、九州出身のシェフ福島さんだ。福島さんは小柄な体格なのに、大きなハーレーダビッドソンに乗っていた。彼は日々、料理長のパンチに意地悪をされ、怒鳴られ、半ば強制的にレストランを追い出されてしまった。きっとパンチは腕のよい福島さんが自分のポジションを脅かす存在になってきたためリスクを感じて、高圧的に追い出したのだろう。福島さんのお兄さんは、九州では有名な暴力団組織に属しているらしく、「パンチの野郎、理不尽なことばかり言いやがって、俺の兄貴に言ってなんとかしてもらおうかな!」なんて言って息巻いていた。パンチは、福島さん以外にも、仕事のできる年配のパート主婦に対しては理不尽な怒り方をして、厨房から追い出していった。パンチは怖くて横柄な人柄だったが、僕や小宮さんにとっては、どこかリーダーとして頼りになる部分があったことは事実だ。
福島さんも静岡の小さな町(確か沼津だったと思う)へ引っ越したのだが、転がり込んだ先は、以前働いていたレストランで男女の仲となった四十代のシングルマザー宅であった。団地のような建物の一室に荷物を運び入れると、福島さんの彼女は麦茶と一緒にスーパーで買ってきたケーキを小さく切り分けて小宮さんと僕のお茶うけにしてくれた。子どもは成人しているらしく、福島さんとその彼女は、そこでゆっくりと生活していくようだった。
彼女が台所でみんなのグラスに麦茶を注いでいたとき、彼女のグラスにはこっそりとアルコールを混ぜているのを僕は見た。二十歳の僕にも、彼女が生活に疲れているのが感じ取れた。帰路、夕方まで長引く真夏の暑さのなか、僕たちは当時いつも聞いていたRun-D.M.Cを大音量で流しながら、彼女がお酒を入れた麦茶のグラスをまぜるような速度で、ゆっくりとゆっくりと国道一号線を走っていった。